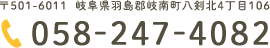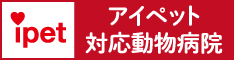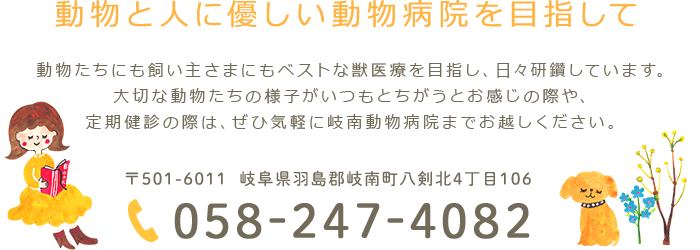- HOME
- 診療案内
診療案内
診療内容
-
一般診療・検査
当院では触診・問診・検査などを行います。動物たちの健康診断もかねて、お気軽にお越しください。
-
去勢・避妊手術
将来的な交配や繁殖を希望されない方には、なるべく早期に去勢・避妊手術を行うようおすすめしています。
-
予防接種(混合ワクチン)
5種、8種、9種など、ワンちゃんのための各種混合ワクチンを用意しています。ご希望に合わせて紹介します。
-
ノミ・マダニ予防
ノミ・マダニが原因で重い病気にかかることもあります。特に川辺にはマダニが多く生息していますので、注意が必要です。
-
フィラリア症予防
ワンちゃんが蚊に刺されると、フィラリア症に感染する恐れがあります。正しい予防で感染から身を守りましょう。
-
狂犬病予防
狂犬病ワクチンは法律で接種が義務付けられています。海外からウイルスが持ち込まれる危険があるので、必ず接種しましょう。
初診・一般診療

はじめて動物を飼われた方、引っ越しなどで途中から当院に通院されることになった方は健康診断のつもりでお越し下さい。
「今日はいつもよりご飯を食べないな…」、「何となく足が痛そうなんだけど…」などほんの些細な変化に気づいてあげられるのはいつも一緒に過ごしている飼い主さんの皆さんです。病気になってからではなく、健康な状態を知っておくのは非常に重要な事となります。
そこで当院では健康診断を実施しています。健康診断は6歳までは一年に1度、7歳からは半年に一度を推奨させて頂いております。触診、問診、血液検査(生化学検査・院内で検査できます)等を実施します。健康な状態を知っていれば、次の検査で何か変化があればすぐに対処できますし、普段と違った様子が見られて受診した際、検査をすれば異常な箇所がすぐに判断できます。検査で異常が見つかった場合、治療、投薬、食事のアドバイスはもちろん、さらに深い検査を行ったり、専門性の高い病院への紹介も積極的に行っています。
家族である動物のために何が一番良いのか飼い主さんとコミュニケーションを取りながら考え、実行していくことが当院のモットーでもあります。
去勢・避妊手術

当院では、将来的な交配や繁殖を希望されない方には、なるべく幼少のときに去勢・避妊手術を行うようお勧めしています。幼少時に行えば精巣も卵巣及び子宮も小さいので傷口が小さく済むからです。
オスは睾丸を全摘出する「睾丸摘出術」を、メスは左右の卵巣及び子宮を摘出する「子宮卵巣全摘出術」を行っています。メスでは、卵巣のみを摘出する方法もありますが、年齢を重ねた際に罹る子宮の病気のリスクを回避するため「子宮卵巣全摘出術」を行っています。
去勢・避妊手術ともにメリット・デメリットがあります。
メリットとしては、乳腺腫瘍・子宮蓄膿症・精巣腫瘍などのリスクが回避できます。また発情期に大きな声で鳴いたり、マーキング(オシッコをスプレーのようにあらゆる場所に吹き付ける)をしたり、メスの場合は出血を気にすることもなくなります。
デメリットとしてはホルモンバランスの変化による肥満が多く見られます。肥満はいろいろな病気を引き起こすことになり兼ねません。これはフードによって予防できます。獣医師と相談して適切なフードを与えてあげましょう。(当院で取り扱いがございます。)
オス・メスともに全身麻酔での手術となります。残念ながら全身麻酔によるリスクを回避することはできません。ですので、当院では手術前検査を必ず行い、少しでも異常が見つかった場合は手術の延期または中止とさせて頂くこともあります。
去勢・避妊手術を受けたわんちゃん、ねこちゃんは受けていないわんちゃん、ねこちゃんに比べると寿命が長いというデータも出ています。
メリット・デメリットをふまえ、大切な家族のQOL(生活の質)の向上を目指しましょう。
※去勢・避妊手術のメリット・デメリットについては院長のブログでも詳細をお伝えします。
予防接種(ワクチン接種)
混合ワクチンは任意接種ですが、最近ではワクチン接種を受けていないとトリミングやペットホテルなど施設が利用できないことも当たり前となりました。 わんちゃん、ねこちゃんの生活を豊かにするためにも、 あらゆる感染症から大切な家族を守るためにも当院ではワクチン接種を勧めています。
わんちゃんはジステンパー・犬パルボウィルス感染症・犬アデノウィルス感染症・ 犬伝染性肝炎を予防するコアワクチン+犬パラインフルエンザウイルス感染症を予防する5種とさらに犬レプトスピラ病 (カニコーラ型・イクテロへモラジ一型)を予防する7種が接種可能です。
ねこちゃんは猫ウイルス性鼻気管炎・猫カリシウイルス感染症・猫汎白血球減少症を予防するコアワクチン (3種)とコアワクチン+クラミジア・フェリス感染症、猫白血病ウイルスによる持続性ウイルス血症の予防を含む5種が接種可能です。
当院ではわんちゃん・ねこちゃんのワクチネーションを絶やさないよう接種予定の前月にはおハガキでお知らせをお送りしています。
予防できるものは予防してあげて、わんちゃん、ねこちゃんの健康の「基礎」 を作ってあげましょう。
*コアワクチン_世界的に重要な感染症に対するワクチンで、全ての犬猫に推奨された間隔で接種すべきワクチンの事。
予防できる各病気について詳しくは随時院長のブログで説明させて頂きます。
ノミ・マダニ予防

大好きなお散歩に出かけるわんちゃん。 近所のパトロールに出るねこちゃん。 外に出る機会があるわんちゃんやねこちゃんは特にノミ・マダニ予防が大切です。 ただし、室内飼いだからといって油断は出来ません。 もしかすると飼い主のあなた自身のどこかに付いて家の中に入ってくることもあるのです。
とくにマダニは SFTS (重症熱性血小板減少症候群)という病気を発生させます。 これはSFTS ウイルスを保有するマダニに噛まれることで発症します。 また発症した動物と濃厚接触することでも感染しますから、 多頭飼いのお宅の他の動物、 わんちゃん、ねこちゃんとのスキンシップで感染する可能性もあります。
すでに岐阜県でも SFTSウイルス遺伝子陽性マダニの確認がされています。
SFTS に感染すると元気・食欲の低下、発熱、嘔吐、黄疸などの症状がみられます。 このような症状がみられたらすぐ病院へお越し下さい。残念ながら有効な治療法が確立されていないため、対処療法を行います。
SFTS はヒトにも感染し、致死率も非常に高い (犬…約40%、猫…約60%、ヒト・・・約30%) 恐ろしい病気です。
当院では年間を通じたノミ・マダニ予防を推奨しています。お薬のタイプもいろいろ取り揃え、飼い主さんの負担が少なく、その子に合ったもので予防していきましょう。
そして外から戻ってきたら全身のマダニチェック、ブラッシングも行いましょう。
フィラリア症(犬糸状虫症)予防
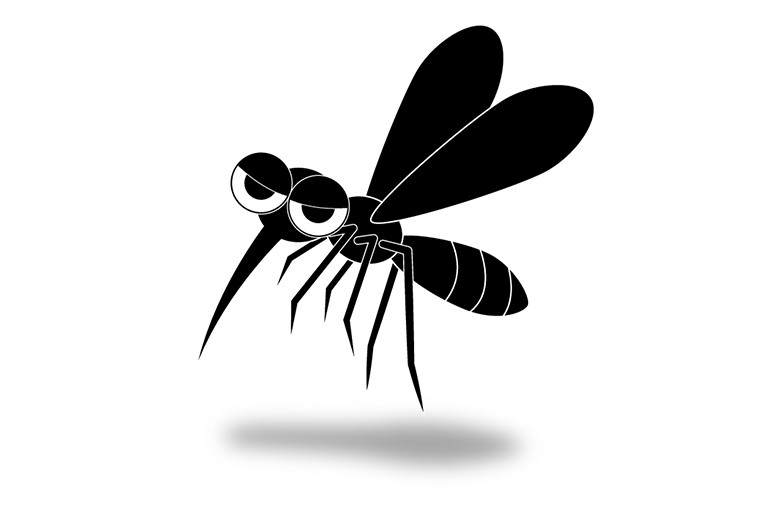
‘フィラリア’と聞くと「犬の感染症」とイメージされる方が大勢とは思いますが、「猫やヒト」にも感染する人獣共通感染症です。
‘フィラリア’は感染した動物の血を吸血した蚊を媒介する感染症です。
感染のメカニズムとしては感染している動物を蚊が吸血すると蚊の体内にミクロフィラリアが移動します。ミクロフィラリアは蚊の体内で成長し幼虫に発育します。その蚊がほかの動物を吸血する際に幼虫が体内に侵入することで感染します。
体内に入った幼虫が脱皮を繰り返しながら成長して、やがて血管に侵入します、成虫になると動物の右心室や肺動脈に寄生して約5~6年生存します。成虫は最大で30mにもなる糸状の寄生虫です。
フィラリア症は「発咳・食欲減退・元気消失・腹部膨満」などの症状がみられますが、初期の段階では無症状であることが多いです。重症になると「腎障害・肝障害・貧血」などを引き起こし最悪の場合には死亡してしまうこともあります。
治療法がないわけではありません。投薬や手術といった方法もありますが、危険や大きな負担がかかります。
このような辛い思いをわんちゃん、ねこちゃんにさせないためにもフィラリア症の予防はしっかり行いましょう。
当院では蚊の飛び始める1ヶ月前から、蚊がいなくなってから1ヶ月後までの投薬をお薦めしています。
近年、酷暑といわれる真夏日が続きますね。このような酷暑の時期は皆さんもあまり蚊に刺されないのではないでしょうか?気温の変化は蚊の活動も変化させています。秋になり涼しくなってきたからといって油断せず、しっかり予防してあげましょう。
※わんちゃんは予防処方にあたりミクロフィラリアが体内にいないか必ず検査を行います。血液で簡単に出来る検査です。万が一、ミクロフィラリアが体内に生存し予防薬を投与すると、アレルギー反応を引き起こし、最悪の場合は死に至るこ事もあるからです。飼い主様のご理解とご協力をお願い致します。
狂犬病予防

狂犬病ワクチン接種は義務です。
まず、わんちゃんを飼った日(生後90日以内のわんちゃんを飼った場合は、生後90日を経過した日)から30日以内にわんちゃんの登録をしなければなりません。その登録が済むと毎年市町村から接種のハガキが届くことになります。(登録は一度だけです。)
当院でも登録が可能です。
市町村から狂犬病ワクチン接種の通知が届いたら、その通知を持参の上ご来院下さい。わんちゃんの食欲や元気があるかの問診、聴診を行い獣医師が接種可能と判断すればその場で接種します。
日本は狂犬病清浄国ですが、世界では今なお、年間55,000人もの方が命を落としています。狂犬病は哺乳類全てに感染し、発症すると死亡率100%の恐ろしい病気です。
コロナ禍が明け、海外への旅行も楽しめるようになりました。
が、アジアでは狂犬病で亡くなる方のほとんどが犬に噛まれて感染しています。愛犬に予防接種をすることで侵入したときの蔓延を防ぎ、人への感染を防御することができます。
近年では狂犬病予防接種の接種率が低くなっています。
日本は大丈夫と思わずに、わんちゃんを飼った義務でもありますので、年に一回健康状態のチェックも兼ねて、狂犬病ワクチン接種を受けに来てください。
わんちゃん、ねこちゃんの食事

アメリカでメラミンが混入されたペットフードを摂食したわんちゃん、ねこちゃんが多く死亡した事件を受け、2007年「愛がん動物飼料の安全性の確保に関する法律」(ペットフード安全法)が制定されました。
このおかげで私たちはあらゆる場所で基準を満たした様々なフードが購入できることとなりました。
しかし、安全だけでいいのでしょうか?人間に置き換えて考えてみましょう。離乳したばかりのあかちゃん、食べ盛り、育ち盛りの成長期、働き盛りの壮年期、ゆっくりと毎日を過ごされる高齢期。食べる量、代謝するエネルギーと必要はカロリー、摂取すべき栄養素。それぞれ違いますよね。
わんちゃん、ねこちゃんも同じです。その子のライフステージに合った食事を与えてあげましょう。
さらに、何か病気が見つかってしまった場合は、通院や投薬も大切ですがその病気に特化した食事に変更してあげることも大切です。
これは「療法食」とか「療養食」と呼ばれるフードで獣医師の指導の下でしか購入することはできません。なぜなら病気が治っても「療法食」「療養食」を続けると逆に栄養のバランスが崩れてしまうこともあるからです。必ず獣医師の判断を仰いでください。
食べるということは命を司る大切な事です。「うちの子にこのフード合っているのかしら…?」「食が細くなってきたような気がするんだけど…。」など些細なことでも結構です。いつでもお気軽にご相談下さい。
治療が終わった飼い主さまへ
食事療法をはじめとした予防医療をお伝えしています。特に高齢のワンちゃんやネコちゃんが病気になった場合は、その子に合った食事の紹介をしています。運動の制限がある場合なども、治療後にお伝えしています。
病気になって動物たちが苦しい思いをしないよう、日ごろからの健康管理を大切にしてあげてください。